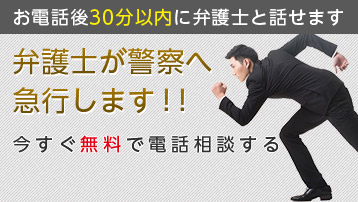窃盗で捕まる確率は何%? 検挙率や後日逮捕されたときの流れ
- 財産事件
- 窃盗
- 捕まる確率

万引き、空き巣、車上ねらい、自転車盗など「窃盗罪」にあたる罪を犯してしまえば、捕まる確率が気になることでしょう。警察庁が公表する資料によると、令和6年における侵入窃盗や自動車盗、ひったくりやすりなどの重要窃盗犯の検挙率は55.7%と比較的高く、そのまま捕まらないだろうなどと思わないほうがよいでしょう。
本コラムでは、窃盗罪として罪に問われる行為から実際につかまる確率、現行犯逮捕と後日逮捕の違い、逮捕後はどうなるのかについて、刑事事件の知見が豊富なベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が詳しく解説します。


1、窃盗罪とは
窃盗罪は最も身近な犯罪のひとつです。ではどのような行為が「窃盗罪」にあたり、どの程度の刑罰が科されるのか、まずは基本事項を確認していきましょう。
-
(1)窃盗罪とは
窃盗罪とは簡単に言えば、他人のものを盗んだときに問われる罪です。
宝石や車、お金といった形のあるものだけでなく、電気や水なども対象です。
刑法第235条で規定されています。
「万引きしようとしたが、警備員に気づかれてできなかった」といった未遂の場合でも、窃盗未遂罪が成立します。
盗む際に暴力をふるうなどした場合は、強盗など別のより重い罪に問われます。 -
(2)窃盗罪の構成要件
盗みであれば、どんなケースでも罪に問われるというわけではありません。
窃盗罪として成立するには、次の3つの構成要件を満たしている必要があります。- ① 他人が占有する財物を盗んだ
- ② 不法領得の意思(盗んだものを自分のものにしようとする意志)があった
- ③ 実際に盗んだ
「他人が占有」とは、他人の管理下にある状態をさします。もともと自分のものであったとしても、誰かに貸した場合はその間は相手が占有していると判断されます。
「不法領得」とは、他人のものを自分のものにして利用・処分しようとすることです。
自己使用目的が前提となるため、嫌がらせのために知人の自転車を盗んで壊した場合には、窃盗罪ではなく器物損壊罪に該当します。 -
(3)窃盗罪の刑罰・時効
窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法第235条)。
未遂でも既遂の場合と刑罰は同じですが、通常は減刑されます(刑法第243条)。
実際に科される量刑は、初犯であるかどうかや、悪質性、被害額などによって変わります。
初犯であれば罰金刑で済んだり執行猶予がついたりする可能性がありますが、被害額が多額であったり組織的に行われていたりする場合には、実刑になったり量刑が重くなったりするでしょう。
なお窃盗罪で何回も刑罰を受けている場合には、「常習累犯窃盗罪」に問われる可能性があります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条)。
刑罰は「3年以上20年以下の懲役」となり、窃盗罪より重くなります。
窃盗罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法第250条)。
ただしこれはあくまで刑事事件の時効であり、7年経過した後でも民事事件として被害者から損害賠償を求められる可能性があります。 -
(4)窃盗罪にあたる行為
一般的に多い窃盗は、万引き、置引き、スリ、ひったくり、空き巣、事務所荒らし、自動車・自転車盗、車上ねらい、賽銭盗といった行為です。
近年、レストランなどで客がお店のコンセントでスマホを充電するなどの行為が散見されますが、お店の許可なく行った場合は電気を盗んだ窃盗罪に問われる可能性があります。
また窃盗罪とよく似た罪に「遺失物等横領罪」があります(刑法第254条)。
たとえば「放置されている自転車に乗る」「拾った財布を持ち帰る」といった、所有者の手を離れたものを自分のものにしようとする行為がこれにあたります。
遺失物等横領罪の刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料」です。
2、窃盗罪で捕まる確率はどのくらい?
窃盗行為が誰にも見つからなかったとしても「そのうち警察が来て捕まるのではないか」と不安に思うことでしょう。
実際に窃盗罪で捕まる確率に公式な統計はありませんが、「検挙される確率」は次のような式で算出できます。
令和6年に全国で警察が認知した窃盗事件の件数は50万1507件、そのうち、検挙された人数は11085人でした。ひとりで複数の窃盗を行っている可能性もあるため、この数字からは正確な検挙率は導き出せません。
一見少なく見えるかもしれませんが、実際には本人の反省や弁償により被害者が警察に通報しなかった、逮捕されたが起訴されなかったなどのケースも少なくないため、「盗みは見つかりにくい」というわけではありません。
なお、窃盗事件の中でも重要窃盗犯(侵入窃盗、自動車盗、ひったくり及びすり)の検挙率は55.7%と突出しており、窃盗の手口の中では検挙されやすいといえるでしょう。
お問い合わせください。
3、窃盗事件の「現行犯逮捕」と「通常逮捕(後日逮捕)」の違い
窃盗事件では「現行犯逮捕」または「通常逮捕(後日逮捕)」になることが多い傾向にあります。では両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
-
(1)窃盗で逮捕されるのはいつ? 現行犯逮捕と通常逮捕の違い
「現行犯逮捕」とは、犯行の最中または直後に行われる逮捕のことです。逮捕状がなくても実行でき、警察官以外の一般人でもできます(刑事訴訟法第212、213条)。
たとえば空き巣に入ったところを警備員に見つかって取り押さえられ、警察に引き渡されるといったケースです。
一方で「通常逮捕」は、警察や検察が裁判所に逮捕状を請求し、その発布を受けてから行う逮捕です(刑事訴訟法第199条)。後日逮捕と呼ばれることがありますが、法律用語ではなくあくまで俗称です。
通常逮捕(後日逮捕)をするためには、容疑者だと疑うに足る「逮捕の理由」と逃亡や証拠隠滅のおそれがあるという「逮捕の必要性」がなければいけません。
警察などが捜査をして逮捕の理由と必要性を裁判所に示し、それが認められた場合にのみ逮捕状が発布されます。
逮捕前に捜査が必要なため、現行犯逮捕と比べて逮捕まで少なからず時間がかかるのが特徴です。 -
(2)通常逮捕(後日逮捕)になりやすいケース
現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の大きな違いは、事件発生時または直後に容疑者が特定されているかどうかです。
被害がすぐには発覚しなかったり、容疑者がすでに現場から逃走していたりするなど、逮捕状の請求までに一定の捜査が必要な場合によく利用されます。
たとえば万引きの場合、店内に不審者がいたとしても誰も犯行を目撃していなければ現行犯逮捕は難しいでしょう。また空き巣の場合、住人が旅行中で被害の発覚まで数日かかることもあります。
そういったケースでは防犯カメラの確認や聞き込みなどをして容疑者を見つけなければいけないため、通常逮捕(後日逮捕)となります。 -
(3)窃盗容疑での逮捕後の流れ
現行犯逮捕でも通常逮捕(後日逮捕)でも、逮捕後の手続きは同じです。
- ① 現行犯逮捕または後日逮捕
- ② 身柄を検察に送致
- ③ 検察が裁判所に勾留を請求、認められれば10日間の勾留
- ④ 勾留の延長が認められればさらに10日間の勾留
- ⑤ 検察官が起訴・不起訴を判断
- ⑥ 起訴されると刑事裁判
逮捕時に身柄を拘束され勾留が決まった場合、起訴・不起訴が決まるまで最大23日間にわたる可能性がありその場合は、警察署の留置場などで過ごさなければいけません。
その間は仕事に行けず、自宅にも帰れません。
ただし万引きなど軽微な犯罪の場合、勾留されないこともあります。
また起訴されても略式裁判になり、即日終結する可能性があります。
4、窃盗で弁護士に相談するメリット
窃盗は殺人などの重大犯罪に比べれば罪としては軽いため、対応によっては身柄の解放や不起訴、執行猶予を得られる可能性があります。そのためには弁護士のサポートが欠かせません。
-
(1)示談につながる
窃盗事件の場合、被害者と示談できるかどうかが最終的な処分内容を大きく左右します。
被害金額が低額だったり犯行が悪質でなかったりする場合、謝罪や被害弁償をすることで示談が成立するケースは少なくありません。
事件後なるべく早く謝罪するなどすれば、そもそも被害者が警察に通報せず、逮捕に至らない可能性があります。
また事件化しても示談しているという事実は、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判での量刑を考慮する判断材料にもなります。
ただし逮捕され身柄が拘束されている場合、当然、本人は被害者に謝罪に出向くことはできません。また被害者が怒りや恐怖心を抱えている場合、謝罪は受け入れてもらえないかもしれません。
そこで弁護士に依頼すれば、留置場にいる本人に代わって示談交渉を図ることが可能です。
社会的信用もあるため、謝罪を拒否していた被害者であっても、話を聞いてくれる可能性が高まります。 -
(2)早期釈放、不起訴、減刑につながる
窃盗は初犯であったり犯行が悪質ではなかったりする場合には、逮捕されても勾留には至らないことはよくあります。
そのためには逮捕直後からの弁護活動が重要です。
弁護士は逃亡のおそれがないなど勾留の必要性がないことを訴え、被害者との示談を進めるなどして早期の身柄解放を目指します。
また勾留されたとしても、不起訴となるために弁護活動を行います。不起訴になれば裁判にはならず、前科もつきません。
起訴されたとしても、証拠の収集や示談により、裁判で執行猶予が得られる可能性もあります。
5、まとめ
自分や家族が窃盗の容疑者となった場合、この先どうなるのか、前科がつくのかなどと不安な気持ちでいるかもしれません。実際に、現場では逮捕されなかったとしても、後日逮捕される可能性は十分にあります。また、警察から連絡が来て、逮捕されなくても取り調べの対象となることもあるでしょう。
いずれにしても最も重要なことは、事件が発覚したら速やかに弁護士に相談し、対応を依頼することです。依頼を受けた弁護士は、逮捕や起訴される可能性を下げるための弁護活動を行い、被害者の方との示談を進めることができます。
一人で悩まず、なるべく早い段階でベリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご連絡ください。刑事事件についての知見が豊富な弁護士がすぐに警察署に駆けつけるなど、できる限りのサポートをし、最善の結果になるように力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています