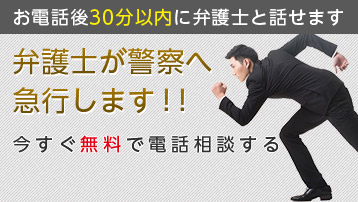エアタグ(Air Tag)を使ったらストーカー? 追跡行為が招く無自覚な犯罪
- 性・風俗事件
- Air Tag
- ストーカー

神奈川県警察では、ホームページで「ストーカー行為は犯罪です」と題し、ストーカー規制法によって規制される行為などを広く公表しています。
令和3年8月26日からは「エアタグ(Air Tag)」などを悪用する行為が規制対象に加えられました。人々の生活様式の変化やインフラの発展にあわせてストーカー行為の態様も変化しており、後を追うかたちで法律も改正を繰り返しています。
本コラムでは、エアタグなどGPSを用いた紛失防止タグなどを用いたことで加害者になってしまったときに問われる罪などを、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。


1、「エアタグ(Air Tag)」など紛失防止タグと犯罪
エアタグをはじめとした紛失防止タグは、忘れ物・落とし物を防ぐために開発されたガジェットのひとつです。そもそもなくしやすい物のありかを知らせるために開発されているので、非常にコンパクトな形状をしています。自分が知らない間にこっそり忍ばせられたり、取り付けられたりしても、簡単に気付けるものではありません。
このガジェットは使い方によっては犯罪行為とみなされます。
-
(1)Air Tagをはじめとした紛失防止タグとは?
財布や鍵といった貴重品をなくしてしまったとき、どこにあるのかを探すことができる便利なアイテムが、Apple社の「エアタグ」をはじめとした紛失防止タグです。忘れ物防止タグ・スマートタグなどの名称でも呼ばれており、タグとスマホが一定の距離から離れるとスマホ側に通知して、忘れ物を防げるという仕組みになっています。
さらに、スマホのBluetoothの電波が届かないエリアでも、同じ紛失防止タグを利用しているユーザーのBluetoothを経由したり、GPS機能を使ったりして、おおよその位置が特定可能です。
紛失防止タグはいずれも非常にコンパクトな大きさで、キーホルダーとして鍵に取り付けたり、カード型なら財布に入れたりして使用するのが一般的です。なかには、裏面が粘着シールになっていて、貼り付けるだけで使用できるタイプのものもあります。 -
(2)「紛失防止タグの悪用」とみなされるケースと発覚のきっかけ
たとえば、相手の許可なく、バッグなど相手の持ち物にタグを忍ばせたり、車の目立たない位置に取り付けたりすることで、相手の現在地を特定しようとした場合は、悪用とみなされます。
ただし、比較的容易に発覚します。たとえば、相手に許可なく持ち物に忍ばせたり、こっそり取り付けられたりしたとしても、紛失防止タグを検知するアプリを活用することで発見できるためです。たとえばエアタグなら、iPhoneの設定から位置情報サービスをONにしておけば、iPhone側の画面に「Air Tagはあなたと一緒に移動しています」と通知されるので、不正なエアタグの存在を検知可能です。
iPhone11以降なら「正確な場所を見つける」機能を使って不正なエアタグの位置を特定できます。iPhoneユーザーではなくても、Apple社が提供している「トラッカー検出」というアプリを使えば同様の方法で不正なエアタグの検知が可能です。
令和5年5月には、Apple社とGoogle社が紛失防止タグの悪用を防ぐために協力することを発表しました。この発表には紛失防止タグを販売しているメーカーの多くも賛同しており、今後はOSのアップデートで対応される見込みです。
なお、iPhoneなどの端末側の機能やアプリを用いて、もしくは持ち物から身に覚えのない不審な紛失防止タグを発見したら直ちに警察に相談すべきですし、そうされる方がほとんどでしょう。
2、紛失防止タグを使った追跡行為が犯罪になる法的根拠
好意を寄せている相手がいれば、今どこで何をしているのか、普段はどのように過ごしているのかを知りたいという願望を抑えられなくなることがあるかもしれません。
しかし、エアタグなど紛失防止タグを使って相手の位置情報を取得する行為は犯罪です。
-
(1)ストーカー規制法による規制内容
ストーカー規制法は、特定の人物に対する恋愛感情や好意の感情、あるいはこれが満たされなかったことへの恨みの感情から、相手につきまとったり、監視していると思わせるような事項を告げたりするなど8類型の行為を「つきまとい等」として禁じています。
つきまとい等を反復すれば「ストーカー行為」です。
さらに、令和3年8月26日からは「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」も規制に加えられました。位置情報無承諾取得等もつきまとい等と同様で、反復して行えばストーカー行為となります。 -
(2)紛失防止タグも「GPS機器等」に含まれるのか?
ストーカー規制法では、承諾なく相手の所持品にGPS機器などの位置情報記録・送信装置を取り付ける行為や、その位置情報を取得する行為を規制対象としています。ここで問題となるのが、エアタグなどの紛失防止タグが「GPS機器等」に含まれるのかという点です。
紛失防止タグは主にBluetoothを利用してその位置を把握する仕様で、GPS機能が備わっていないものも少なくありません。すると、GPS機器等にはあたらないのでストーカー規制法に違反しないと考える人がいるかもしれませんが、この点を「適法」と考えるのは危険です。
実際に、令和4年12月には、同僚だった女性の車に無断でエアタグを取り付けて位置情報を取得していた男が、ストーカー規制法違反の容疑で書類送検された事例があります。
ストーカー規制法の条文も、技術的な進歩や新技術の開発を想定したうえで「GPS機器」と特定せず「位置情報記録・送信装置」といった表現を使用していることから、安易に「GPS機能が備わっていないから適法」と考えてはいけません。 -
(3)ストーカー規制法の罰則
ストーカー規制法に違反しても、直ちに処罰されるとは限りません。
つきまとい等や位置情報無承諾取得等は、一度限りであれば罰則がないので、まずは警察署に呼び出されて、警察本部長などによる「警告」や公安委員会からの「禁止命令」を受ける流れが一般的です。
ただし、これらの行為を複数回にわたって反復している場合は「ストーカー行為」となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。
また、禁止命令を受けたうえでさらに同じ行為を繰り返すと「禁止命令違反」となり2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が、禁止命令を受けたうえで別の行為によるつきまとい等・位置情報無承諾取得等があれば6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。
3、ストーカー規制法違反で逮捕されるとどうなる? 刑事手続きの流れ
ストーカー規制法違反の容疑で警察に逮捕されると、その後はどうなるのでしょうか?
刑事手続きの流れを確認していきます。
-
(1)逮捕・勾留によって最大23日間の身柄拘束を受ける
警察に逮捕されると、警察の段階で最大48時間、検察官のもとへと送致されて最大24時間の身柄拘束を受けます。ここで、検察官が「身柄拘束を続けて捜査を進める必要がある」と判断すると勾留が請求され、裁判官が許可すると10~20日間の勾留を受けます。
逮捕・勾留をあわせると身柄拘束の期間は最大で23日間で、この期間は自宅へ帰ることも、会社や学校へ行くことも、家族や上司・同僚などに連絡を取ることも許されません。
ストーカー規制法違反の容疑で23日間にもわたって社会から隔離されてしまえば、家族との離散、会社からの解雇など、さまざまな不利益が生じるおそれがあります。
逮捕されてしまった、あるいは逮捕の危険を感じているなら、弁護士への相談を急いでください。早い段階で弁護活動を開始し、被害者との示談交渉や捜査機関へのはたらきかけなどを行うことにより、逮捕の回避や早期釈放が期待できます。 -
(2)検察官が起訴・不起訴を判断する
勾留が満期を迎えて捜査が終了すると、検察官が「起訴」または「不起訴」を判断します。
ここで検察官が起訴を選択すれば容疑者の立場は「被告人」となり、刑事裁判を待つ身となります。
起訴されて被告人になると、さらに被告人として勾留を受けて、警察署の留置場から拘置所へと移送されます。
被告人としての勾留は実質無期限なので、刑事裁判が終了するまで釈放されません。
素早い社会復帰を目指すなら、検察官の段階で不起訴が選択されるか、起訴されたとしても「保釈」を実現する必要があります。不起訴となれば刑事裁判が開かれないので勾留の必要もなく、直ちに釈放されます。
また、保釈が許可されれば日常生活を送りながら指定された期日に出頭して刑事裁判を受けることを許されるので、それ以外の時間は自宅で家族と過ごすことも、会社へ行くことも可能です。
ただし、不起訴や保釈といった処分を得るためには、真摯(しんし)な反省や家族などによる監督強化の誓約などが影響します。
どのような対策が不起訴・保釈の可能性を高めるのかはケースごとに異なるので、経験豊富な弁護士のサポートが欠かせません。 -
(3)刑事裁判で有罪判決を受けると刑罰が科せられる
検察官の起訴から1~2か月後に初回の刑事裁判が開かれます。以後、おおむね1か月に1度のペースで公判が開かれ、数回の審理を経て判決が言い渡されるのが一般的な流れです。
ストーカー規制法に違反したことが事実であれば有罪となり、法律が定める範囲内で刑罰が科せられます。
裁判官が言い渡す判決の内容は、さまざまな事情が考慮されます。被告人が深く反省しており被害者への謝罪や弁済を尽くしているなどの事情があれば、ストーカー規制法が定める罰則の範囲内でも軽い方向へと傾きやすくなり、執行猶予や罰金といった有利な処分が得られる可能性が高まるでしょう。
一方で、犯行の態様が悪質で被告人の反省が見られなかったり、被害者が厳しい処罰を求めていたりすると、判決が重い方向へと傾いてしまいます。
状況に適した判決を得るためには、被告人の事情を刑事裁判で示さなければなりません。ストーカー規制法違反事件の弁護実績が豊富な弁護士に依頼して、過剰に重い刑罰が科されないよう、サポートを受けましょう。
4、まとめ
エアタグをはじめとした紛失防止タグは、財布や鍵といった貴重品を探しやすくしたり、忘れ物を防いだりするのに役立ちます。しかし、ご自身が「意中の相手の行動や自宅を知りたい」と考えて紛失防止タグを悪用してしまった場合は、ストーカー規制法違反で捜査の対象になってしまう可能性がある犯罪行為です。
逮捕や厳しい刑罰を回避するためにも、弁護士に相談して解決に向けたサポートを受けましょう。ストーカーの被害者・加害者となってしまいお悩みなら、ストーカー事件の解決実績のあるベリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています