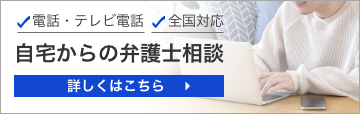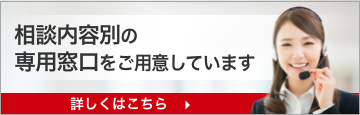【企業向け】減給の上限(限度額)は? 具体的な計算方法などについて
- 労働問題
- 減給
- 上限

事業を経営していると、従業員が不祥事を起こしたり、会社に対して損失を与えてしまい対応に苦慮することがあります。
この場合、思い浮かぶのが給料のカットによる減給処分です。とはいえ、減給は無条件に行えるものではなく、条件や上限が定められています。
この記事では、従業員の給与を減額できる条件や減額の上限、計算方法まで弁護士がわかりやすく解説します。
1、減給処分の上限(限度額)と期間は?
-
(1)減給とは
そもそも減給とは、会社が従業員に対して、決められた給与から一定額を減じて支給することを言います。従業員は会社と雇用契約を結んでおり、雇用契約では従業員の就労義務と、会社の賃金支払い義務が定められています。したがって、原則として、会社は雇用契約で定められた給与を従業員に支払う義務があり、一方的に給料を下げることはできません。
ただし、事情によっては給料の減額が認められることもあります。たとえば、従業員の言動が懲戒処分にあたるような場合です。通常、服務規律やその他の企業秩序や利益を維持する制度として、懲戒処分が設定されています。懲戒処分の方法として、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告などがあります。従業員の言動が、「減給」としての懲戒処分に該当するならば、減給処分を行うことも認められます。 -
(2)減給には上限がある
減給ができる場合でも、その金額に上限があることに注意しましょう。労働基準法第91条に、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない」という定めがあります。つまり、「減給」は平均賃金の1日分の半額を超えてはならないという上限があるのです。
さらに、減給の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないという規定もあります。これは、一人の従業員に対して、複数の減給理由がある場合のことです。一回分の賃金支払い期間中に、複数の懲戒事由が起きてそれぞれについて減給をする場合には、その減給の総額が、一回の賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけないという意味です。もし、10分の1を超える減給がある場合は、超えた部分の減給は、次の賃金支払期に行う必要があります。
2、減給する場合の上限(限度額)の計算方法
では、具体的に減給の上限を計算する方法について確認しておきましょう。
なお、以下の計算は、労働基準法第91条に基づき「従業員の問題行動に対する懲戒処分として減給処分を行う場合」にのみ適用されます。懲戒以外の事情で減給する場合には適用されませんので、ご注意ください。
1回の減給処分における減給限度額は、以下の計算式で計算します。
この計算式でいう「平均賃金」は、以下の方法で割り出します。
- ① 減給処分の直前の賃金締日から3か月分の「賃金の総額」を計算します。
- ② 減給処分の直前の賃金締日から3か月分の「総日数」を計算します。
- ③ ①で得られた「賃金の総額」を②の「総日数」で割ります。
- ④ ③の計算結果が最低額を下回らなければOKです。なお。最低額は次の式で計算します。
- ⑤ ①「賃金総額」÷「減給処分の直前の賃金締日から3か月間の従業員の出勤日数」×0.6
③の計算結果が⑤で得られた額を上回るときは、③の金額が減給限度額の計算における「平均賃金」です。
③の計算結果が⑤で計算した金額を下回るときは、⑤で計算した金額が、減給限度額の計算における「平均賃金」です。
このようにして得られた平均賃金の1/2が減給処分の上限となります。
3、減給が可能なケースについて
懲戒処分以外でも、減給ができる場合があります。では、減給ができるのはどんな場合なのか具体的に見ていきましょう。
-
(1)会社と従業員で合意が成立したとき
会社から一方的に行う場合と異なり、会社と従業員の間で合意が成立していれば減給が可能です。その根拠は、労働契約法第8条にあります。
労働契約法第8条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
給与は、もともと会社と従業員の間の雇用契約で定められています。この契約そのものを新しく合意して変更すれば、それ以降は新しい契約が有効となります。したがって、新しい雇用契約によって以前よりも低い給与を決定すれば、結果としてそれによって減給できることになります。
たとえば、新型コロナウイルス感染症による業績悪化のため給与の支払いが苦しくなり、倒産も見通される状態だとします。このような場合は、従業員にその状況を説明し、会社や雇用を維持するためには給与を減額しなければならないという事情を伝えて理解を求めることが重要です。従業員も解雇されるよりは減給の方がいいと理解してくれる可能性があります。 -
(2)就業規則の変更による減給
雇用契約ではなく、就業規則を変更することによって減給することも考えられます。
労働契約法第9条には、次のように定められています。労働契約法第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
この規定によれば、労働者と雇用主が合意していれば、労働者の不利益になる労働条件の変更も可能だということです。そして、「就業規則」には賃金規程も含まれますから、基本給の額を引き下げや、各種手当を廃止なども、合意すれば可能となります。
さらには、労働契約法第10条では以下のように規定されています。労働契約法第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
これによると、就業規則の変更に対する同意を拒んだ社員がいた場合でも、次の条件を満たせば、給与を下げることも可能だということです。
- ① 倒産危機を回避するためなどやむを得ない状況
- ② 従業員に生ずる不利益も社会通念上容認できる
- ③ 会社が従業員に説明を尽くした
このような状況があれば、社員全員の同意がなくても減給が可能となります。
-
(3)人事評価規定に沿った減給
会社の規定で、人事評価が一定基準に満たなければ減給する旨が定められている場合、その人事評価規程に基づいて減給を行うことが可能です。ただし、人事評価自体が公平に行われていることが大前提です。
-
(4)懲戒処分としての減給
就業規則の懲戒事由に減給処分が規定されており、かつ、従業員の言動が減給処分に該当した場合は、懲戒としての減給が可能です。方法としては、基本給や諸手当の額自体は変えずに「減給10分の1を3か月命ずる」という期限を決めた方法と、降格により基本給または役職手当自体を減額して、持続的に減給をする方法があります。
4、減給による労使間のトラブルを防ぐ方法は?
-
(1)懲戒処分としての減給の場合
懲戒処分としての減給を行う場合には、会社からの一方的な処分行為に当たるため、特に慎重を期する必要があります。減給処分は比較的重い処分ですから、従業員からの反発を受けてトラブルになる可能性が高いためです。
まず、今回の処分の対象となった行為が、就業規則の懲戒処分の規定にしっかり合致していることが重要です。さらに、過去の事例からみても相当性があるといえるかも検討する必要があります。
また、処分自体は正当であっても、減額できる金額に間違いがないか、減額する期間は相当かといった点も事前に検討しましょう。
そして、従業員に対しては、処分に至った経緯や事情をできるだけ説明し、処分は規定上やむを得ないこと、ただし、今後の活躍を期待していることを伝えて過度に追い詰めないようにしましょう。とにかく、大きなトラブルに発展しないように配慮することも会社の円滑な運営のためには重要なことです。
なお、処分に至った経緯については、必ず書面に残しておくようにしましょう。後から万が一トラブルになった際に、会社の判断の正当性を立証する必要があるからです。特に、言った言わないという争いが続くようなことが無いように、会社側の判断のプロセスや、従業員への説明の状況などは出来る限り記録に残すようにしましょう。 -
(2)合意による減給の場合
合意による減給は、従業員と合意した後に、従業員から合意など存在していないという文句を言われないようにすることが重要です。合意の内容を必ず書面で残し争いにならないようにしておきましょう。
5、まとめ
本記事では、会社が不祥事を起こした従業員に対して減給処分を行うことができる場合と、その注意点について解説しました。減給は従業員の生活に大きな影響を与えますので、従業員からの反発も予想されます。できればトラブルを回避して円満に手続き進めたいものです。そのためには、法律の規定をしっかり守り、証拠を残すなどの準備をしっかりしたうえで臨むことが大事です。
ベリーベスト法律事務所では、一般企業法務に関して多数の経験を持つ弁護士が在籍し、企業側からのご相談を承っております。事情に応じた丁寧なアドバイスを心がけておりますので、ご不安な点があればいつでもご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています