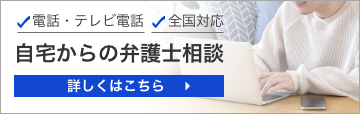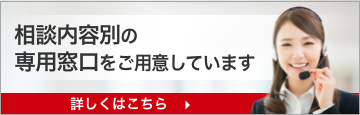毒親からの被害を警察に訴えたい。逃れるためにできることは?
- 一般民事
- 毒親
- 警察

血縁関係にある親子であっても、親から日常的に肉体的暴力を受けたり、精神的虐待を受けたりするケースは少なくありません。あなた自身が成人になっても親に変わらず暴力を振るわれていたり、経済的な圧力を受けていたりするのであれば、なんとか毒親から逃れたいと思うことはごく自然なことです。
未成年者であれば児童相談所に対処してもらえる可能性がありますが、成人しているときはどうすればよいのでしょうか。今回は、毒親に対して警察や弁護士などの第三者がどのように介入できるのかについて解説いたします。
1、子どもは毒親を訴えられないの?
親が子どもに暴力をふるう、恐喝する、虐待を繰り返すなど、問題がある家族に関する問題が顕在化しています。その代表的なキーワードが「毒親」です。
まずは、毒親とはどのような親を指すのかについて解説します。
-
(1)毒親とは?
毒親という言葉は1989年にアメリカで発売された「TOXIC PARENTS」に由来しています。本の著者はアメリカの精神医学者であるスーザン・フォワードで、邦題は「毒になる親~一生苦しむ子供~」です。
本の中には育児放棄や虐待、言葉による暴力などの手段で子どもをコントロールしようとする親が描かれています。「毒親」とは前述の著書を略して生まれた言葉です。親という立場や権限を利用し、子どもに対して以下のような加害行為をする親を指します。- しつけや教育と称した肉体的な暴力
- 子どもを否定する、過度に不安を与えるような精神的な暴力
- 子どもを監視する、物事がうまくいきそうなタイミングで妨害行為をする
- 子どもの失敗に対して追いつめる、責める、ばかにする、ののしる
- 親の身勝手な考え、夢・希望を子どもに無理やり押し付け、刷り込ませる
- 育児放棄など子どもにまったく興味を持たず、逆に自己責任として子どもに求める
- 性的な虐待を与える
-
(2)毒親による暴力などに子どもは耐える義務がある?
子どもは、親に上記のような理不尽なことをされたとしても、ひたすら耐えなければならない義務があるのでしょうか?
そのような義務はまったくもってありません。
相手が自分を生んだ母親や養っている父親であっても、子どもにもひとりの人格があり、親の操り人形ではありません。親の希望通りに生きる必要はなく、親の肩代わりをする必要もありません。
法律上においても、たとえば親の借金を、保証人でもない子どもが背負う必要は一切なく、さまざまな手続きによって相続を放棄することも可能となっています。
2、毒親による被害を訴える際の罪状は?
親に日常的にされている行動でも、警察に訴えることができることがあります。
●恐喝罪
お金などを要求するため親が暴行や脅迫を行い、結果、あなたが恐怖のあまりそれに応じた場合、成立する可能性があるでしょう。
●暴行罪
殴る蹴るなどの身体的な暴力はもちろん、着衣を無理やり引っ張るなど、あなたの身体に影響をおよぼす行為をした場合にも成立することがあります。
●窃盗罪
あなたの財布からお金をくすねるなどの窃盗行為があった場合、親を窃盗罪で告発することが可能です。
●名誉毀損(きそん)罪
うそや虚偽の事実を周りに吹聴し、子どもの地位や立場を脅かす行為は名誉毀損罪として罪を問えることがあります。内容が真実だったとしても同様です。
●脅迫罪
「殺すぞ!」「殴るぞ!」「いうことを聞かなければ死んでやる」といった言葉を用いて、あなたを脅迫した場合、脅迫罪に抵触する可能性があります。
●迷惑防止条例違反
たとえ家族であっても、子どもを24時間監視する、つきまとうなどの行為をすれば、迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。
ただし、恐喝罪と窃盗罪、横領罪については、刑法第244条に定められた「親族間の犯罪に関する特例」が適用されます。あなたの親が実親であれば、「直系血族」に該当するため、刑が免除されます。つまり、あなたの物を盗んだり、あなたの不動産に不法に占拠したり、あなたを恐喝して金品を取り上げたという事実があったりしたとしても、たとえ逮捕されても不起訴となるか刑罰を免除されます。
それでも、暴力を受けている最中などに警察に連絡することには意味があります。なぜなら、警察官の判断で興奮状態の親を緊急逮捕されることもありますし、あなたがこれ以上身体的被害を受けることを食い止めることもできるかもしれません。また、実際に被害を受けているという、動かぬ証拠を残すことができます。
3、子どもが毒親被害から逃れるためにできること
あなたが未成年の場合は、児童相談所などに相談してください。子どもの身に危険があると判断されれば保護してくれるでしょう。しかし、親子であるがために、通常であれは処罰される罪を犯したとしても免除されてしまうこともあるのが毒親被害の盲点です。毒親被害から逃れるために覚えておく必要があるポイントについて解説します。
まずは、毒親とはどのような親を指すのかについて解説します。
-
(1)毒親と戸籍上の縁は切れない
たとえ毒親であっても、戸籍上の縁を切ることはできません。これは日本の法律上、また制度上も存在しないため、仕方ない部分であるといえるでしょう。また未成年の場合、親には扶養義務がありそれを免れることもできません。
そのため、実家暮らしであれば家を出て別に暮らすなど、とにかくできるだけ早いタイミングで物理的な距離を取ることが大切です。ただし、相続が発生したときは、双方に影響があります。あなたの財産を親に渡したくないときは、弁護士に相談しながら遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。また、親からの財産を受け取りたくないときは、相続開始から原則3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。 -
(2)親族関係調整調停や分籍手続きが可能
「親族関係調整調停」を家庭裁判所に申し立てるのもひとつの方法です。親族間でのトラブルを調停による話し合いで解決しようとするものです。話し合いによって双方合意ができれば調停調書が作成され、裁判による判決と同様に効力を持ちます。ただし親族関係調整調停は親との「関係修復」は想定していますが、「関係断絶」は想定していません。仲介を担う調停員も親世代の方が多いこともあり、弁護士などを間に入れなければ親族関係調整調停を行うハードルが高い可能性があります。
また、もうひとつの方法として「分籍手続き」も利用できます。一般的に親が再婚する際に子どもに配慮して籍を分けるような場合に利用されますが、毒親とのトラブルで心理的に距離をおきたい場合も有効です。分籍する当事者が分籍届書を提出することで簡単に手続きが行えます。戸籍謄本などが必要となります。
4、被害者である子どもの戸籍に閲覧制限は付与可能?
毒親被害に遭ったことで戸籍を分籍したとしても、親であれば戸籍を閲覧することが可能です。それを避けるためには、住民票および附票の両方に閲覧制限をかける必要があります。これを住民基本台帳事務における支援措置といいます。
ただし申出を受けた市区役所などが,独自に判断することはできません。まずは警察や女性センターなどに事情を説明し、支援措置が必要であるという認定をしてもらう必要があります。その際は、毒親に遠慮することはありません。緊急性があることをある意味大げさにしっかりと訴える必要があります。
認定後は、本人以外は閲覧することができません。しかし、支援措置は1年間と定められているため期間延長を都度申請してください。また申請時には、毒親はもちろんのこと、毒親が雇った弁護士であっても開示しないように依頼することが大切です。
役所が弁護士へ簡単に開示してしまうトラブルを受け、総務省でも弁護士からの請求は加害者本人からの請求と同様に扱う旨の通知をしています。
5、代理人として弁護士にできること
毒親による脅迫や暴力も犯罪行為に抵触するものです。しかし、前述のとおり司法が親子関係や家族の問題に介入するのは難しい部分があります。
ただし、状況のやり取りを第三者が明確にわかる証拠がある場合は、刑事責任を問えなくても、返還を求めたり、損害賠償請求を行ったりすることができる可能性があります。
たとえば、借用書を作成した上でお金を貸したケースや、あなたが学費などの振込先として登録し、入金しておいた口座を親に預けた結果、親が使い込んだケースです。これらの状況であることが明らかな場合、民事責任を問うために損害賠償を請求することができるでしょう。
しかし、その際にも「話し合い」というプロセスが必ず発生します。しかし、多くの場合、毒親と話し合おうとしても、冷静に状況を伝え、理解してもらうとすることは非常に難しいことです。
そこで、弁護士に依頼し、話し合いや交渉をしてもらうことをおすすめします。もし、すでに離れて暮らしているときは、相手にあなたの住所を知られないように対応してもらうことも可能です。状況によっては弁護士と警察が連携して動くこともできるでしょう。まずはひとりで悩まず、相談してください。
6、まとめ
毒親による肉体的かつ心理的ストレスは子どもに大きな影響を与えます。子どもは閉鎖的な家庭という場に置かれ、泣き寝入りしてしまうことや、自殺など取り返しのつかない事態に発展してしまうこともあります。
たとえ親であっても、ひとりの人間である子どもに対し、権力を武器に脅迫や暴力などを与えることは決して許されることではありません。家庭内のトラブルだけに声をあげづらい側面がありますが、第三者を入れることで解決への道に向かうケースもあります。
毒親被害にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所川崎オフィスにご相談ください。親身になって法的なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています